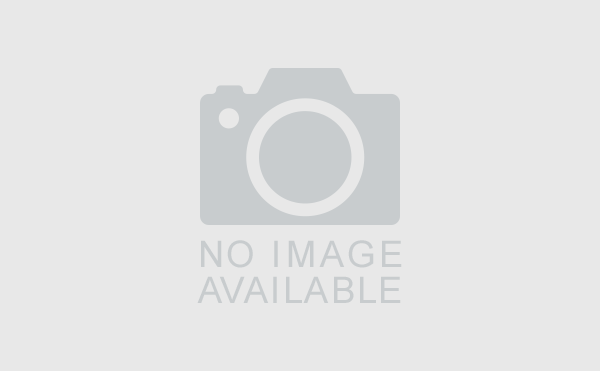児童福祉法とは?
「ウェルビーイング」とは、身体的・精神的・社会的に良好な状態にあることを指す概念であり、子どもの権利や福祉の基盤となっています。日本では、戦後まで全ての児童を保護する政策がなかった歴史があります。本記事では、子どもの権利と福祉の根幹をなす「児童福祉法」の成立背景から、現代に至るまでの変遷を詳しく解説します。
児童福祉法の成り立ち
近代以前の日本では、子どもの人権という考え方は広く浸透していませんでした。明治から昭和初期にかけては貧富の格差が広がり、困窮により命を落とす子どもや、人身売買の被害に遭う子どもが後を絶ちませんでした。また、劣悪な環境下での児童労働も蔓延するなど、子どもの人権を侵害する深刻な問題が山積していました。当時、民間の篤志家や宗教家による児童保護の活動は存在していましたが、国全体の子どもを網羅的に保護する法律や施策は未整備でした。
1945年、日本は第二次世界大戦で敗戦。敗戦直後の日本は、食糧不足や住宅不足に加え、戦争で親や家族を失った戦災孤児が社会問題として浮上しました。彼らは生きるために物乞いや盗みをせざるを得ない厳しい状況に置かれていました。政府は同年9月に「戦災孤児等保護対策要綱」を決定し、戦災孤児の保護を最優先事項としましたが、これらの施策は一部の子どもを対象とした応急的なものに過ぎませんでした。
しかし、この混乱期が日本の児童福祉政策を本格的に動かすきっかけとなりました。1946年に日本国憲法が制定され、その理念に基づき、翌1947年に児童福祉法が制定されました。この法律は、満18歳に満たない者を児童と定義し、すべての子どもたちの福祉を実現することを目的としていました。このように、日本の児童福祉施策は、敗戦後の社会的な危機と新憲法の理念を背景に、ようやく本格的にスタートしたのです。
改正児童福祉法
児童福祉法は、時代の変化に応じて何度も改正されてきました。中でも、2016年の改正は、従来の理念に新たな視点を加える画期的なものでした。
【改正前の児童福祉法 第1条・第2条】 改正前の条文は、日本国憲法の理念に基づき、国民が子どもの健全な育成に努め、国や地方公共団体が保護者とともにその責任を負うことを定めていました。
【改正後の児童福祉法 第1条・第2条】 改正後の条文では、まず第1条に「児童の権利に関する条約の精神にのっとり」という文言が明記されました。これにより、子どもが適切に養育され、生活が保障されるだけでなく、心身の健やかな成長と発達、そして自立が図られる権利を持つことが明確に謳われました。 第2条では、国民が子どもの意見を尊重し、「最善の利益」を優先して考慮するよう努めることが定められました。また、保護者が子どもの育成に第一義的責任を負うことも明確にされました。
この法改正は、国際的な理念を国内法に取り入れた結果です。「児童の権利に関する条約」は、1989年に国連総会で採択された国際条約であり、子どもを大人と同様に人権を持つ主体的な存在として捉え、生きる権利、育つ権利、意見を表明する権利などを保障しています。 また、この時期、欧米諸国では、救貧的・慈恵的な「ウェルフェア(福祉)」に代わり、「よりよく生きること」「自己実現の保証」といった意味合いを持つウェルビーイングの考え方が児童福祉の分野で広がりを見せていました。この理念は日本にも波及し、従来の児童福祉のあり方を見直す機運が高まったのです。こうした背景から、2016年の法改正では「児童の権利に関する条約」と「ウェルビーイング」の理念が児童福祉法に明文化されるに至りました。
児童福祉法と障害児福祉施策
児童福祉法は、障害児の福祉施策とも密接に関わる法律です。法律では、身体または知的障害のある満18歳未満の子どもを「障害児」と定義し、その支援を定めています。特に2010年の法改正では、障害児支援制度が一元化され、サービス利用者が支援内容をより明確に理解し、利用しやすい体制が整備されました。具体的には、障がいの種類や法律によって異なっていたサービスが、通所・入所といった利用形態によって整理されました。
そして、2024年6月には、さらに新たな改正児童福祉法が施行されます。今回の改正は、子育て支援や自立支援に加え、障害児への支援を強化する内容となっています。
障害児支援の向上に向けた具体的な施策
今回の法改正では、障害児支援の分野で、以下のような具体的な施策が盛り込まれています。
- 児童発達支援センターのサービス向上 「児童発達支援センター」は、障害のある未就学児が通所する施設であり、自立に必要な知識や技能、集団生活への適応訓練などを提供しています。これまで、その役割や機能が明確でなく、民間の「児童発達支援事業所」との役割分担が曖昧な状況にありました。今回の改正では、センターの役割が「幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援」や「地域の障害児通所支援事業所に対する助言・援助」などとして明確に規定されました。これにより、障害児支援全体の質の向上が図られます。
- 放課後等デイサービスの利用年齢の拡充 「放課後等デイサービス」は、放課後や長期休暇中に、障害のある子どもや発達に特性のある子どもを支援する通所施設で、学童保育のような役割を担っています。これまでの利用対象は「就学している障害児」に限られており、義務教育終了後、専修学校や各種学校に通う子どもは対象外でした。しかし、今回の改正により、市町村長が認める場合に限り、これらの学校に通う15歳から17歳の子どもも利用できるようになりました。これは、多様な進路を選ぶ障害のある子どもたちが、切れ目のない支援を受けられるようにするための重要な変更です。
まとめ
戦後の混乱期に制定された児童福祉法は、国際的な理念や「ウェルビーイング」の考え方を取り入れながら、時代のニーズに合わせて進化を続けてきました。特に、2016年の法改正では、子どもを単なる保護対象から、権利を持つ主体的な存在として捉え直す大きな転換が図られました。また、2024年の改正では、障害児支援の体制をより強化し、支援の質向上と利用機会の拡大を目指しています。
すべての子どもたちがウェルビーイングを実現できるよう、児童福祉法は今後も社会の動向や変化に対応し、常に改正が求められる重要な法律であり続けるでしょう。