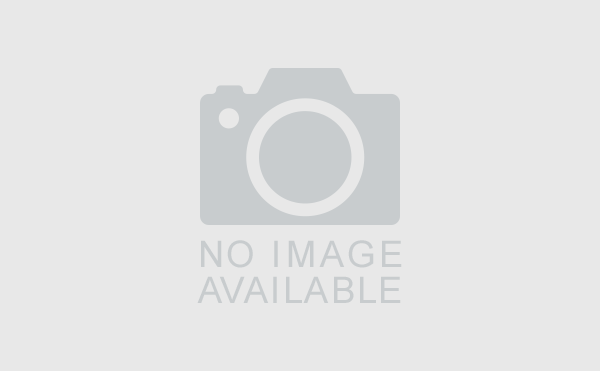障がいの3区分と発達障がいとは?― 障害者総合支援法と障がい特性について ―
「障害者総合支援法」は、障がいを持つ人々が日常生活や社会生活を円滑に営むための包括的な支援を定めた法律です。この法律は、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、そして政令で定められた難病などを持つ18歳以上の人々を対象としています。行政は、施策を効率的に実施するため、これらの障がいを身体、知的、精神の3区分に発達障がいを加えて整理しています。
障がい3区分
以下では、この3つの主要な障がい区分と、それに含まれる発達障がいの特性について詳しく解説します。
身体障がい
「身体障害者」は、「身体障害者福祉法」に基づき、視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、咀嚼機能、肢体不自由、内部障がいなど、永続的な身体上の障がいを持つ18歳以上の者で、身体障害者手帳の交付を受けた者と定義されます。
【視覚障がい】
視覚機能の永続的な低下により、学習や生活に支障がある状態です。全盲から弱視、視野狭窄など、その程度は様々です。文字の読み書きや移動に困難を感じることが多く、白杖や盲導犬、ガイドヘルパーを伴う方もいれば、外見からは分かりにくい方もいます。
【聴覚・言語障がい】
聴覚障がいは、音や話し声が聞こえにくい、またはほとんど聞こえない状態を指します。全く聞こえない方、片耳だけ聞こえる方、補聴器を使用する方など多様で、音声からの情報取得が困難である点が共通しています。言語障がいは、発音が不明瞭であったり、話すリズムがスムーズでなかったりするなど、言葉でのコミュニケーションに支障が生じる状態です。
【肢体不自由】
病気やけがで身体の動きに関わる器官が損なわれ、日常生活動作が困難な状態です。歩行、筆記、物の持ち運びなど、障がいの程度は人によって大きく異なり、必要なサポートも多岐にわたります。
【内部障がい】
心臓、腎臓、呼吸器、免疫、肝臓などの内臓機能が病気やけがで損なわれ、日常生活に困難を感じている状態です。疲れやすい、長時間の移動が制限されるなど、症状は多様です。外見からは障がいが分かりにくいため、ヘルプマークなどの利用が増えています。
知的障がい
「知的障害者福祉法」は、知的障がい者の自立と社会参加を促進することを目的としていますが、法律には明確な定義がありません。そのため、都道府県知事が交付する療育手帳の判定結果に基づいて対象者が決まります。
【知的障がいの特性】
知的機能の障がいが発達期に現れ、学習や日常生活に様々な困難を抱えることが特徴です。抽象的な思考や物事の判断、問題解決などを苦手とする方がいます。社会的なルールを理解できず、奇異な行動を取ることがありますが、これは意図的なものではなく、周囲の状況を理解するのが難しいためです。外見からは判断しにくく、誤解を招くこともあります。
精神障がい
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(精神保健福祉法)では、統合失調症や気分障害、知的障がい、その他の精神疾患を「精神障害」と定めています。また、「障害者基本法」では、精神障がいがあるため継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受ける者を「精神障害者」と定義しています。
【精神障がいの特性】
精神活動に関わる身体や心の機能の変調により、日常生活に困難を抱えています。主な精神疾患には、統合失調症や気分障害、パニック症などがあります。症状には波があり、外出や人との交流、物事の判断などが困難になることがあります。発症の原因や時期、症状は個人差が大きいですが、適切な治療や服薬、周囲の配慮によって症状をコントロールし、安定した生活を送っている方が大半です。
発達障がい
「発達障害支援法」は、発達障がいの早期支援を目的としており、「自閉症、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害など、脳機能の障がいで通常低年齢で発現するもの」と定義しています。
【自閉症(ASD)】
他者との社会的関係の形成、言葉の発達、狭い興味やこだわりを特徴とする障がいです。コミュニケーションにおいては、言葉や表情、視線などを用いた相互的なやりとりや、感情の読み取りに困難を感じます。感覚過敏や鈍感さを持つこともあります。
【アスペルガー症候群】
言葉と知的発達の遅れがない、対人関係の障がいです。特定の興味や行動に固執することがあります。会話で自分のことばかり話してしまうなど、コミュニケーションに困難を抱えますが、興味のある分野では専門家並みの知識を持つ方も多くいます。
【学習障がい(LD)】
知的発達に遅れがないにもかかわらず、読み書きや計算などの特定の能力の習得に著しい困難がある状態です。読むこと、書くこと、算数に困難を伴うタイプに分けられます。一人ひとりの認知特性に合わせた対応が必要で、「Learning Differences(学び方の違い)」と表現されることもあります。
【注意欠陥・多動性障がい(ADHD)】
年齢や発達に不釣り合いな注意力、衝動性、多動性を特徴とする行動の障がいです。落ち着きがない、待てない、注意が持続しにくいといった特徴が挙げられます。多くの場合、7歳以前に症状が現れ、学業や社会生活に影響を及ぼします。
まとめ
障がいには、一人ひとり異なる様々な種類や特性があります。行政は支援施策を効率的に実施するため、障がいを大きく3つの区分に分けていますが、重要なのは、このような多様性を認識し、個々人の特性を理解することです。地域生活支援や福祉サービスを利用する際には、それぞれの障がいの種類と特性を把握しておくことが有益です。