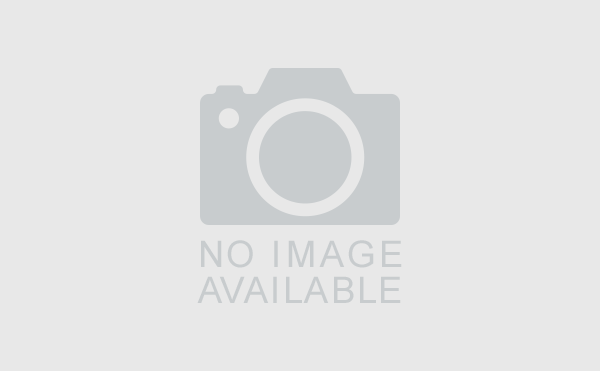障害者総合支援法の成り立ちについて
―障がい者施策の歩み―
はじめに
現在の日本には、障がいのある方が利用できる多様な支援制度が存在します。「障害福祉サービス」や「地域相談支援」、市町村主体の「地域生活支援事業」などが代表例です。時代と共に多様化・複雑化するニーズに応えるため、支援制度の拡充や法整備は幾度となく繰り返されてきました。その集大成が、現在の障がい福祉の根幹をなす「障害者総合支援法」です。
本稿では、この法律がどのような歴史的背景と人々の願いのもとに生まれてきたのか、その歩みを詳しく解説します。
第1章:日本の障がい福祉、その黎明期
日本の本格的な障がい福祉施策は、第二次世界大戦後に始まります。それ以前の公的支援は、主に「軍事扶助法」に基づき、戦争で負傷した軍人(傷痍軍人)に限られていました。これは、富国強兵という国策のもと、国家への貢献者に対する恩恵的な意味合いが強いものでした。
1945年の敗戦後、GHQの指導のもとで日本国憲法が制定され、個人の尊厳と基本的人権の尊重が謳われると、社会福祉に対する国家の責務が明確化されます。この理念を具現化するため、福祉制度の根幹となる「生活保護法」(1946年)、「児童福祉法」(1947年)、「身体障害者福祉法」(1949年)の「福祉三法」が整備されました。これらは戦後の混乱期における重要なセーフティネットとなりました。
さらに、官民一体の福祉供給体制の基礎として「社会福祉事業法」(1951年)が、障がいのある子どもの教育の保障として「学校教育法」(1947年)による「特殊教育」が始まりました。ただし、これは健常児とは別の場で教育を行う「分離教育」であり、後の「共生社会」の理念とはまだ隔たりがありました。このように、日本国憲法を起点として、日本の障がい福祉の骨格が形成されていったのです。
第2章:ノーマライゼーションという新たな潮流
1950年代、デンマークから発信された「ノーマライゼーション」という理念が世界に広がります。これは「障がいのある人が、ない人と同等に当たり前の市民生活を送る社会こそが正常だ」という考え方で、従来の「保護」「隔離」中心の福祉観を覆す画期的なものでした。
この理念は世界的な潮流となり、1975年には国連で「障害者の権利に関する宣言」が採択されます。さらに国連は、1981年を「国際障害者年」(テーマ:完全参加と平等)、続く1983年から10年間を「国連障害者の10年」と定め、障がい者の機会の平等と社会参加を強力に推進しました。
こうした国際的な動向は日本の国内政策にも大きな影響を与え、障害者対策に関する長期計画が策定されるなど、法改正が推進されました。この時期を経て、日本社会にもノーマライゼーションの理念が深く浸透していきました。
第3章:利用者本位への転換と新たな課題
1990年代、財政的な制約も背景に社会福祉制度の構造改革が議論されます。当時の障がい福祉サービスは、行政がサービス内容や施設を決定する「措置制度」でした。これは行政が責任を負う一方、利用者には選択の自由がなく、画一的なサービスになりがちという課題を抱えていました。
この状況を打開するため、2003年に「支援費制度」が施行されます。従来の「措置」から、利用者自身が事業者と「契約」を結び、主体的にサービスを選択できる仕組みへと歴史的な転換を果たし、「利用者本位」が大きく前進しました。 しかし、支援費制度にも新たな課題が生まれます。
- 障がい種別ごとの縦割り: サービス体系が身体・知的・精神で分かれ、利用しにくい。
- 精神障がい者の対象外: 制度の谷間に置かれていた。
- 地域間格差: 自治体ごとにサービスに格差が生じていた。
- 就労支援の不十分さ: 一般就労を目指す支援が弱かった。
- 支給決定プロセスの不透明さ: サービス量の決定基準が分かりにくかった。
これらの課題を解決し「共生社会」を実現するため、2005年に「障害者自立支援法」が制定されました。これにより、障がいの種別を超えて共通の仕組みでサービスを利用できる「一元化」が実現し、就労支援の強化なども図られました。
第4章:障害者総合支援法の制定と理念の実現へ
「障害者自立支援法」は多くの前進をもたらしましたが、利用者負担のあり方(応益負担)などが議論を呼びました。当事者の声を受け、2013年に同法は「障害者総合支援法」へと改正・改称され、新たなスタートを切ります。
この改正の最も重要な点は、法律の冒頭に「基本理念」が明記されたことです。これは、個人の尊厳、共生社会の実現、身近な場所での支援、社会参加の機会確保、自己決定の尊重、社会的障壁の除去という、施策が目指すべき社会の姿を明確に示しました。 この理念に基づき、いくつかの大きな改正が行われました。
- 【対象範囲の拡大:難病患者等へ】 障がい者の定義に「難病等」が加わり、対象となる難病患者の方も障がい福祉サービスを利用できるようになりました。
- 【「障害程度区分」から「障害支援区分」へ】 サービスの必要度を判定する基準が変更されました。心身の状態に関する80項目の調査などを通じ、より多角的かつ個々の障がい特性をきめ細かく反映した判定が可能になりました。
- 【重度訪問介護の対象者拡大】 手厚い在宅介護である重度訪問介護の対象が、従来の重度の肢体不自由者に加え、重度の知的障がい者・精神障がい者にも拡大されました。
まとめ
日本の障がい福祉は、戦後の「救済」から「保護」「分離」を経て、ノーマライゼーションの理念と出会い、「自立」と「共生」を目指す道へと大きく舵を切ってきました。その歩みは、当事者や関係者の絶え間ない声によって切り拓かれた歴史です。
「障害者総合支援法」はその結晶であり、現在の日本の障がい福祉を支える柱です。3年ごとの見直しが定められており、常に時代の変化に応え続けることが期待されています。この法律が生まれた背景と、その根底にある「共生社会の実現」という理念を深く理解することは、社会の一員である私たち一人ひとりにとって非常に重要です。その理解こそが、誰もが尊重され、共に支え合う豊かな社会を築く一助となるでしょう。